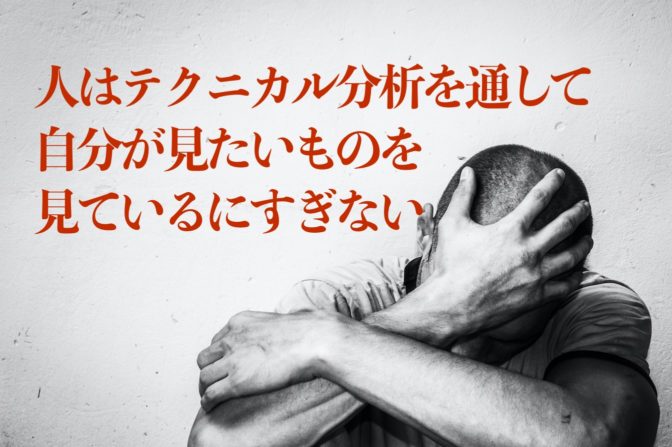
人はテクニカル分析を通して自分が見たいものを見ているにすぎない
エリオット波動理論擁護派から多数の反論が…
昨日アップした記事「エリオット波動理論が海外でどう評価されているか…知りたい?」の反響が大きすぎて、戸惑い気味です。
多くのメールを頂いたのですが、そのほとんど(というか全部)が、エリオット波動擁護派の人々からの怒りメールでした。
「もっとエリオット波動を勉強してから発言するべき!」
「直近の動きもすべてエリオットで説明できる!」
「エリオット波動理論の解釈が間違っている!」
「エリオット波動理論は年々進化していて、精度が高くなっているのを知らないの?」
ある程度の反論メールはあると思っていましたが、これほどまで多いとは予想外でした。色々と議論があるのは良いことだと考えていますので、この機会に大いに盛り上がることを期待したいです。
学術的結論から述べれば、テクニカル分析は「オカルト」の類である
こんなことを言っては身もふたもないのですが、学術的結論から言えば、テクニカル分析そのものが全く否定されている事実をまずは知っておくべきでしょうね。
テクニカル分析、つまり過去の値動き(4本値)をベースに未来の値動きを予想する分析法は、ある意味「オカルト」の類(たぐい)であるとされているわけです。
詳しくは以下の本をお読みください。


少し長いですが引用します。
まず、チャート分析の大前提となっているのが、将来の相場変動は、過去の値動きに大きな影響を受けるということである。学術の世界でチャート分析が無視されているというのは、まさにこの点にある。金融理論では、相場の将来の変動は過去の値動きとは一切無関係であることが想定されている。これを専門用語ではマルコフ性というのだが、こうした性質を仮定することで数学的に扱いやすくなるだけでなく、実証データからもマルコフ性を否定する明白な証拠は得られていない。
(中略)
まず、効率的市場仮説の世界を想定してみよう。そこでは、相場の動きは全てランダムで、予測は不可能だ。しかし、ユール・スルツキー効果により、チャート分析はさまざまなトレンドやらパターンやら(と見えるもの)を導き出す。人は、それらのトレンドやパターン(と見えるもの)を見て、将来の相場の動きを予知したような気持になる。言うまでもなく、完全にランダムな世界では、これらは全て偶然の産物を見誤っただけの幻想であり、将来の値動きについて意味のあることを語ってくれるものではない。つまり、チャート分析はまやかしであり、人々を惑わすだけの代物に過ぎない。これが、正規の金融理論によるチャート分析の評価だ。
(中略)
逆に、テクニカル分析を信じる人にとっては、当たったケースをいくつも探し出すことができるはずだ。そして、その成功例だけが印象に残るため、テクニカル分析の有効性がしっかりと心に刻まれる。また、当たらなかったケースについても、テクニカル分析にはさまざまな分析手法があるので、そのどれかを持ち出して組み合わせたりすれば、「こうやっていれば当たったのだ」と後で説明を付けることはいくらでも可能だ。つまり、「やり方によっては当たっていたはず」の事例として認識され、チャート分析の有効性に疑問を投げかける材料にはならない。
「こんなに当たるすごいチャート分析がある」とか、「このチャート分析を使えばリーマンショックも予想できた」などというたぐいの話は、大体この手の心理的なトリックによるものだ。
”人はテクニカル分析を通して自分が見たいものを見ているにすぎない”
要約すれば以下の通り。
- チャート分析はまやかしである
- チャートに出現するパターンの多くは幻想である
- チャートの動きを予測できた!というのは単なる後付けである
- 人間はランダムな中に法則性を発見し、ありもしないトレンドを認識してしまう
- 人はテクニカル分析を通して自分が見たいものを見ているにすぎない
なかなか辛辣ですね。まさにチャーティストを完全否定するかのような主張です。
特に「人はテクニカル分析を通して自分が見たいものを見ているにすぎない」は、相場の本質を捉えるうえで最も適切な表現なのではないでしょうか。
『投資と金融にまつわる12の致命的な誤解について』の著者は田淵直也氏。日本長期信用銀行やUFJパートナーズ投信(現・三菱UFJ投信)を渡り歩き、金融マーケットに長く携わったプロ中のプロです。
相場は本来予測不能である(不確実である)というスタンスで、多くの投資関連著書を発表しています。いわゆるランダムウォーク派ですね。相場を予測することのバカバカしさを説き、予測をベースとした投資法に警鐘を鳴らします。
テクニカルにドハマリしている人(テクニカル信者)にこ読んで欲しい良書です。きっと目が覚めるはず。
市場がランダムウォーク(不確実性)ならば”勝機”はゼロか?
市場がランダムだからといって、まったく勝機がないわけではありません。100%ランダムということはなく、わずかなトレンド(ランダムではない相場=確率的な偏り)を利益に変える方法は残されています。
非ランダム性(=偏り)は人間心理から生まれるとされています。価格変動の大部分がランダムウォークであることを大前提とし、市場に非ランダム性が発生した瞬間をいかに捉えるか?わずかな偏りを捉える優位性。ここに私たち個人投資家にとっての勝機が存在します。
本来、相場はカオスであり「人はテクニカル分析を通して自分が見たいものを見ているにすぎない」「相場は敗者のゲームである」ことを認めること。ここからスタートしなければなりません。
テクニカル分析は投資家にとっての”ロマン”にすぎない…この現実から目を背けるべきではありません。現実を直視することで、市場にわずかに存在するリターンの源泉を見つけ出すことに一層集中できるはずです。

































































